金沢で「生きづらさ」を感じ、「自信がない」と悩んでいませんか?このページでは、サービス利用や料金など、皆様からよくいただくご質問とその回答をまとめています。
T&Nリサーシャに関するよくあるご質問
T&Nリサーシャの理念やサービス全体に関して、よくお寄せいただくご質問とその回答をまとめました。私たちの支援の根幹にある考え方について、ご理解を深めていただければ幸いです。
※各サービス(もの作り、視える化など)に関する具体的なご質問は、それぞれのサービスページにもQ&Aを設けておりますので、そちらも併せてご覧ください。
当施設の理念に関するよくある質問
Q. T&N リサーシャの名前の由来は?
T&N リサーシャの正式名称は「T&N 活動支援研究所(T&N Research and Support Center for Activity)」です。これは、金沢大学大学院医学系研究所保健学専攻の準教授だった精神科作業療法士の故 関 昌家 によって名づけられました。しかし、堅苦しく呼びにくいため、英語名の Research(リ) and Support(サ) Center(セ) for Activity(ア)の頭文字から「リサーシャ」という愛称が生まれました。ちなみに「T&N」は、創設者の息子たちの名前の頭文字であり、その遺志を継いでほしいという思いが込められています。
Q. キャラクターのデザインは?
当施設のキャラクター「アリンちゃん」は、「何でもアリ」の蟻をモチーフにしています。「どんな状態でも、どんなことでも良い。何かを始めるのに駄目なことはない」という想いを込め、障がいを持つ20代の女性がデザインしてくれました。この経験が自信となり、彼女が地域で活躍するきっかけにもなった、当施設の理念を象徴するキャラクターです。
サービスのご利用について
Q. 週に何回通えばいいですか?
特に決まりはありません。お一人おひとりの状態やご希望は違うからです。例えば、週に1回の方もいれば、2週間に1回の方もいます。無理のない範囲で、最適なペースを一緒に探していきましょう。
Q. 本人が通いたがらない場合はどうすれば?
ご本人に通う意思がない場合、無理強いは禁物です。まずはご家族だけでご相談いただくことも可能です。ご家族がサービスを理解し、ご本人とのより良い向き合い方を一緒に考えることから始めましょう。
Q. プライバシーは守られますか?
はい、厳守いたします。ご相談内容や計測したデータが、ご本人の同意なく外部に漏れることは一切ありません。ご家族や他の支援機関と情報を共有する際も、必ずご本人の許可を得てから行いますのでご安心ください。
Q. どれぐらいで変化が見られますか?
個人差があるため一概には言えませんが、多くの方は1〜3ヶ月程度でご自身の心身の状態とデータの関連性に気づき始めます。しかし、大切なのは期間ではありません。データを通してご自身の「安定のサイン」や「不調のサイン」を見つけ、ご自身で対処していく力を育んでいくプロセスそのものが重要だと考えています。
Q. 料金について教えてください。
各サービスの料金については、こちらの利用料金ページをご覧ください。
Q. どのような服装で行けばいいですか?
特に服装の指定はありませんので、リラックスできる普段着でお越しください。 施設内では他の方と共同でスペースを利用するため、皆様が気持ちよく過ごせるよう、 清潔感のある服装を心がけていただけますと幸いです。 もの作りなどで服の汚れが心配な方は、エプロンをお持ちいただいても構いません。
Q. 駐車場はありますか?
申し訳ありませんが、当施設には専用の駐車場はございません。 お車でお越しの際は、お手数ですが、周辺のコインパーキング等の有料駐車場をご利用ください。 詳細は、アクセス情報ページに地図を掲載しておりますので、そちらをご参照ください。
Q. 遠方に住んでいてもカウンセリングを受けられますか?
申し訳ありませんが、現在は対面でのカウンセリングのみとなります。当施設のカウンセリングは、専門スタッフとの対話に加え、もの作りなどの活動中のご様子を客観的に評価させていただくことを大きな特徴としております。そのため、オンラインでのご提供が難しいのが現状です。何卒ご理解いただけますと幸いです。
Q. 本人がひきこもっていても、家族だけで相談できますか?
はい。ご本人が来所されていない状態でも、家族面談や家族会をご利用いただけます。実際に、ご家族が先に支援を利用される中で、本人の状態が変化していったケースもあります。
こころの状態に関するよくある質問
Q. 診断名がなくても利用できますか?
はい、ご利用いただけます。T&Nリサーシャでは、診断名の有無にかかわらず、ご自身の「生きづらさ」に悩むすべての方を対象としています。ご自身の状態を整理し、理解を深めるために通われている方も多くいらっしゃいます。
Q. こころの病とは?
こころの状態には、体の状態と同じように脳や神経の働きの影響が関係している可能性があります。これは「脳の機能の状態変化」というひとつの視点であり、決して「性格の良し悪し」で判断されるものではありません。
例えば、統合失調症、うつ病、双極性障害(躁うつ病)などは、現在の医学では多くの要因が複雑に影響した状態として理解されています。遺伝的な特性、生まれる前後の発達の影響、日々の生活環境やストレス、睡眠・栄養・人間関係など、さまざまな因子が重なって現れる状態と考えられています。
この考え方は、全ての人に同じように当てはまるものではありません。人によって背景や影響の受け方は異なり、診断や治療方針は専門の医師・医療機関で判断されるべきものです。
この多様な要因を理解することで、
・「性格や人間性が悪いから」
・「弱いから」
といった誤解を避け、ご自身や大切な人の状態を 正しく理解する助けになります。
もし、こころの状態に心配がある場合は、まず専門の医療機関でご相談されることをおすすめします。医療・福祉サービスと当施設の支援を組み合わせて活用することで、より確かな理解と改善を目指すことができます。
Q. こころの不調で、どのようなことが起こりますか?
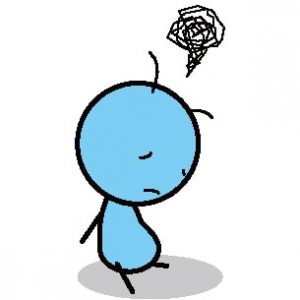
多くの方から共通して聞かれるのは、『気力・知力・体力が以前のように働かない』という感覚です。例えば、今まで出来たことが満足にできなくなったり、物事を覚えにくくなったり、すぐに疲れてしまったり、という状態も見られます。
特に、何もする気が起きない状態が長く続くと、体力が大きく低下することがあります。この状態が数カ月に及ぶこともあり、他者との接触を避けて『引きこもり』の状態に繋がるケースも少なくありません。ご自身やご家族だけで抱え込まず、まずは専門の医師や相談機関に相談することをお勧めします。
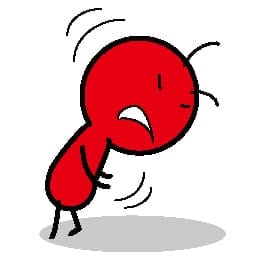
一方で、統合失調症や双極性障害などでは、ほとんど動けない状態から一転して、必要以上に活動的になることがある、と言われています。しかし、体力が低下しているため、その期間は長くは続かない傾向があります。さらに、うつ病では、状態が改善してきた時期に自殺のリスクが高まることがあるため、注意が必要だとされています。
薬の副作用について
こうした状態の変化は、病気だけでなく、薬の副作用によっても起こり得ます。治療薬は脳に作用する化学物質から出来ているためです。そのため、薬を飲み始めてから何らかの異変を感じたら、ご自身の判断で服薬を止めたりせず、必ず医師に相談してください。
Q. 家族から見た場合、どのような様子が見られますか?
・家から出ようとしない、出かけても夜しか出ない。
・人に会いたがらない。
・一人でブツブツ何か言い、時には笑っていることがある。
・何もせず、ごろごろ寝てばかりいる。
・いつも暗い表情で、泣いてばかりいる。
・話す内容がよくわからない。
・お風呂にも入るのを嫌がり、服も着替えない。
・窓を閉め切り、掃除もしない。
Q. ご本人はどのようなことで悩んでいることが多いでしょうか?
・仕事に行きたくても自信がない。
・何もしたくないけれど、どうにかしたい。
・人と話すのが苦手でも何とかしたい。
・何かしたくても何していいか分からない。
・家から出るのが億劫、でもどうにかしたい。
・自分をどうしていいか分からない。
・孤独を感じている。
・助けてと言えない。
・生きるのに疲れてしまった。
・誰かに見張られているような気がする。
Q. 病気の診断名が変わることがありますか?
はい、変わることはあります。こころの不調は脳の機能的なゆらぎであり、その影響は広範囲に及ぶことがあります。そのため、一人の人に複数の症状が現れることは珍しくありません。そして、人によって症状の組み合わせや程度が異なるのが特徴です。
環境や時間による症状の変化
また、病気の診断は、症状だけでなく、その症状がどのくらいの期間続いているかも考慮されます。脳は環境によって変化するため、発病から時間が経つにつれて症状が変化し、診断名が変わる場合があるのです。
しかし、大切なのは診断名に一喜一憂しないことです。状態の変化には環境が大きく関わっています。当施設では、診断名に大きく左右されず、お一人おひとりの状態に合わせたサポートを提供しています。
各プログラムに関するよくある質問
Q. なぜ、もの作りを行うのでしょうか?
もの作りは、単に手を動かすだけでなく、計画性、集中力、問題解決能力、そして完成の喜びを通じて「自己肯定感」を育む多面的な活動です。私たちは、この活動を通して、ご自身の「こころの状態」、「行動パターン」、「集中力や忍耐力」、そして「ストレスへの対処」といった多角的な側面を体験的に学び、成長のきっかけを掴んでいただきたいと考えています。
Q. 『視える化』では、具体的にどのようなデータを計測するのですか?
加速度センサーや振動計を搭載した独自の計測システムを使用し、もの作りにおける動作の速度、時間、力の加減、作業回数などを記録します。そして、これらのデータから、ご自身では気づきにくい集中力の持続時間や、心身の疲労度などを客観的に分析します。
Q. 計測に使用するセンサーは身体に装着するのですか?
いいえ、身体に直接装着することはありません。計測に使用するセンサーは、革細工で使う木槌や、織物で使う織り機といった道具に取り付けられます。そのため、感覚過敏などで身体に物を着けるのが苦手な方でも、安心してご利用いただけます。
ご家族向け支援に関するよくある質問
Q. 家族会には、どのような方が参加されていますか?
ひきこもりや精神疾患、発達障害、HSPの特性を持つ方のご家族など、様々な状況のご家族が参加されています。
Q. 人前で話すのが苦手なのですが、参加しても大丈夫ですか?
もちろん大丈夫です。無理にお話しいただく必要はありません。他の人の話を聞いているだけでも、得られるものはたくさんあります。安心してご参加ください。
Q. 本人のデータを見ることに抵抗があるのですが…。
データの共有は、必ずご本人の同意を得た上で、ご家族・ご本人・スタッフの三者が納得できる形で進めます。データはあくまで相互理解を助けるツールであり、無理強いすることは決してありません。ご懸念やご不安な点も、面談の中でお気軽にご相談ください。

